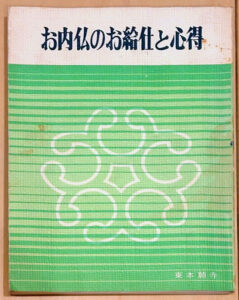第四十九回 お内仏の荘厳(お華束二)


先月も言及しましたように、十月後半から三月にかけて報恩講のシーズンです。
当寺も本山も11月に勤修します。ということで、今回は報恩講限定の華束の飾り方の話になります。
報恩講の飾りは須弥盛(しゅみもり)になります。
写真上が須弥盛の形です。去年から、在家のお内仏の飾りを説明しておりますので、本来なら、在家用の見本を用意しなければなりませんが、実際のところ、須弥盛を、おとりこし(在家でお勤めをする報恩講の名称)にお供えする家庭は、都市文化圏では皆無に近い状態です。
おとりこし自体、行われる家庭も減ってきました。当寺の御門徒でも数えるほどしかありません。本当は、浄土真宗で一番重要な行事なのですが。
一方、北陸・越後では、いまだに、おとりこしに、お内仏へ須弥盛のお供えをしているようです。さすが、真宗王国であり、米どころと申しますか。
では、今回のテーマ、須弥盛に入りましょう。
今回の写真は、当寺のものではなく、十月に報恩講を勤修された、お寺からいただいたものです。
頂上に果物(みかん、地域によっては柿)が一つ、団子の山型盛、また果物が数個、そのあとを、たくさんのお団子が敷き詰められた形ですが、青と赤に線状に染められています。これは、須弥山(しゅみせん)をかたどったものといわれています。
須弥山というのは、インドの仏教思想の山で、入門書を読むと、よく出てきます。サンスクリット語ではSumeru(シュメール)と書きます。
この須弥山という山は形が変わっていて、上部が大きな円盤状、そこから円柱状態、そして、下部になると、花が広がるように、段々と円が大きくなっていきます。供笥に供えた須弥盛は、その状態をあらわしているものです。
頂上には帝釈天(たいしゃくてん)が君臨し、中間地点では、東西南北の四方を、四天王、二十八部衆が守護をしていると言われています。
須弥壇の語源もここからです。須弥壇というのは、二枚目の写真のように、お内仏では、阿弥陀様前の、ひときわ目立つ大きな壇です。色とりどりですが、赤が多くつかわれています。ですから、赤色の線が入っているのでしょう。
真宗の須弥盛は赤色と、もう一色、青色が使われています。一枚目の写真をあらためて見てください。円盤下部から青色、その下が赤色、また、その下が青色の線となっております。
青の代わりに、緑色を使われるところもありますが、信号機で緑色を青というようなたぐいでしょう。
この色の配色ですが、漆を具現する黒は食物には適しないという理由だと存じますが、赤と青を使う、はっきりとした理由はわかりません。そのようなことを説明してある文献が存在してませんので。
ですが、教化にたずさわった先生たちによると、煩悩(ぼんのう)をあらわしているということです。
煩悩、久しぶりに出てきた言葉です。連載の最初の方を見ると、毎回のように出てきています。
それだけ、業が深いものと申しましょうか。人間の心に潜む鬼、悪魔にたとえられます。
さて、その解釈の仕方ですが二通りに別れます。
最初に説明をするのは、普通の火と水の関係です。火は水をかけることによって消える。つまり、赤は煩悩で、青はそれを抑えようとする心、をあらわしているといいますか。仏教全体の教えで、打敷と水引、軸の赤い中枠と青い外枠は、その火と水の関係からきているということです。
次の解釈は、真宗、独特のものでしょうか。
仏様の教えに三毒というのがあります。三毒というのは、人間を悩ます三つの根本的な煩悩のことです。
よく、煩悩の数は108と言われますが、108といのは、この三つの煩悩が、細かく分かれたものです。
この三つというのは、貪(とん)、瞋(しん)、痴(ち)と呼ばれております。
「貪」は貪欲です。欲という言葉がつくように、物を欲しがる心です。あれが絶対に欲しい、とか、あの人がうらやましい、ということがこうじて、時には人間性を変えてしまう、よくないものです。
「瞋」は瞋恚、怒りのことです。自分の思うようにならない、怒りというのは、なかなか、抑えることはできません。その怒る感情が煩悩ということです。
三つの目の「痴」。病いだれに、知という漢字の通り、「知識がかたよって、真理を理解していないことが、わからずに生きている」という状態です。愚痴という言葉があるように、世の中のことを自分の物差しではかり、文句を言ったり、不満をためることです。この煩悩も、ときには、大変な結果を引き起こします。
三毒すべて、ろくなものではないのですが、浄土真宗では、最初の二つの煩悩について言及しています。
宗祖親鸞聖人の教えに善導大師(ぜんどうだいし)の「二河白道(にがびゃくどう)のたとえ」というのがあります。
この二河というのは、水の川と火の川です。水の川は「貪」火の川は「瞋」を指します。
ある旅人が、道を西の目的地に向かって歩いていました。すると、後ろから何者かが追いかけてきました。旅人は逃げようとしても簡単に逃げることができません。
なぜなら、南には火の川、北には水の川があるからです。どちらの川も、激しい流れで、どんどん迫ってきます。その結果、通る道も細くなってきました。
後ろには戻れない、右にも左にも行けない。ちゅうちょをしていたら、どちらかの川におちる状態、道は前方にあるのですが、両川に覆われて行けるかどうかわからない細い道(約4・5寸の幅)だけです。
そのとき、前方つまり西の方角から『どんなことがあっても、おそれずに前に進み、私のところに来なさい』と不思議な声が聞こえてきました。逆に後ろからは『前に行ってはいけない、死ぬぞ』の声が。
最終的には、前方の不思議な声に従って、その白くて細い道を、ためらわずに進んでいくことで、旅人は無事に西の目的地にたどりつきます。
拙僧にはまだ難しくて、うまく説明ができませんが、声をかけてくださったのが、阿弥陀様で、西(浄土)にたどり着いて助かったということ自体が、煩悩から逃れた、苦しみや悩みのない悟りの境地に入ったということです。
須弥盛の赤線と青線の間が、白い道でしたら、もう少し細くしなければなりませんが、デザイン上の都合ということにしておきましょう。
仏様に飾られている須弥盛を目にすることで、聖人の「二河白道のたとえ」を思い浮かべることも、報恩講の迎え方の一つでしょう。
そして、その白い道こそが、親鸞聖人の残された尊い教えと自覚をして、その教えの道を自ら歩んでいるのか確認することが大切ではないでしょうか。